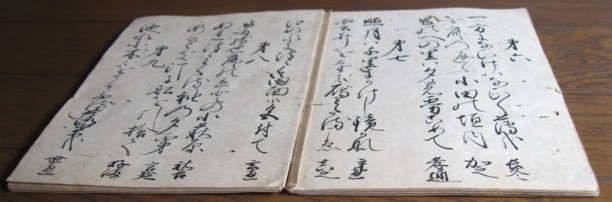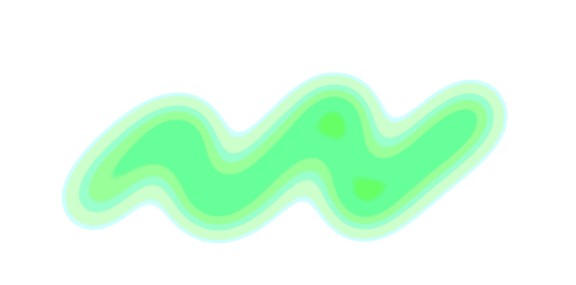
������f�ށA���̂ق��֘A���邱�Ƃ����グ�Ă��܂��B
�摜�ɂ͓ޗNJG�{�ȊO�̂��̂��g���Ă��܂��B
�C���[�W�摜�Ƃ������ƂŁB
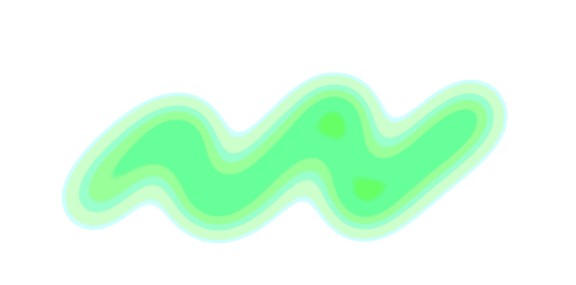
������f�ށA���̂ق��֘A���邱�Ƃ����グ�Ă��܂��B
�摜�ɂ͓ޗNJG�{�ȊO�̂��̂��g���Ă��܂��B
�C���[�W�摜�Ƃ������ƂŁB
���q�d���i��������@���イ����j
�]�ˑO���̓ޗNJG�{�E�G���Ȃǂ̏��ʎҁB�����鍋�ؖ{���肪����\���ƁB
���ʏ��i���������@�������̂ނ��߁j
�������̌��ƁB�]�ˈȗ��A�������q��҂�1�l�Ƃ��ڂ���A�܂����̏��ʂɂȂ�Ƃ����`�{�����Ȃ��Ȃ��B�^�Ƒ��w��̑��q�x�̋ɂɂ́u��ʋǓ�����q�V�M�v�Ƃ���A�u���e���̑����v�Ƃ��L����Ă���B����͐l������Ɏ�����^������̂Ƃ��Ē��ӂ����B
�V�ю��i�����т��݁j
�{�������̑O���1�`2���قǔz����锒���B�ܒԂ̏ꍇ�͖{��1����������ɂ��Ă邪�A���̏ꍇ�͖{���̔����̏ꍇ����ł���B�T���ĉ��^�{�ɂ͋H�ł���B
��G���i���킦�̂��j
����p�E�_�[��ɂ����痿�B��a�G�̊痿�̑�\�I�Ȃ��́B������P�������ėp����B���q�ɂ͋ɂ߂čׂ������̂���e�����̂܂ł���B
�œܕ\���i����������т傤���j
�ʼn_�Ƃ��B���E���E�ԂȂǂ̐F�������|���A�_�`�̖͗l���o�������́B�ޗNJG�{�̒��ł͂��Â���i�ɑ����B�Â��ޗNJG�{�̑}�G�̂������ɂ́A����Ɨގ������F���g���Ă���A���Ƃ̊֘A�����ӂ����Ƃ���ł���B
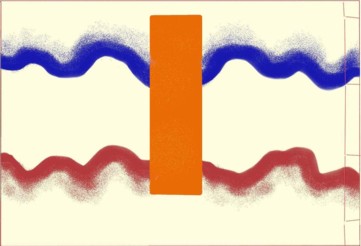
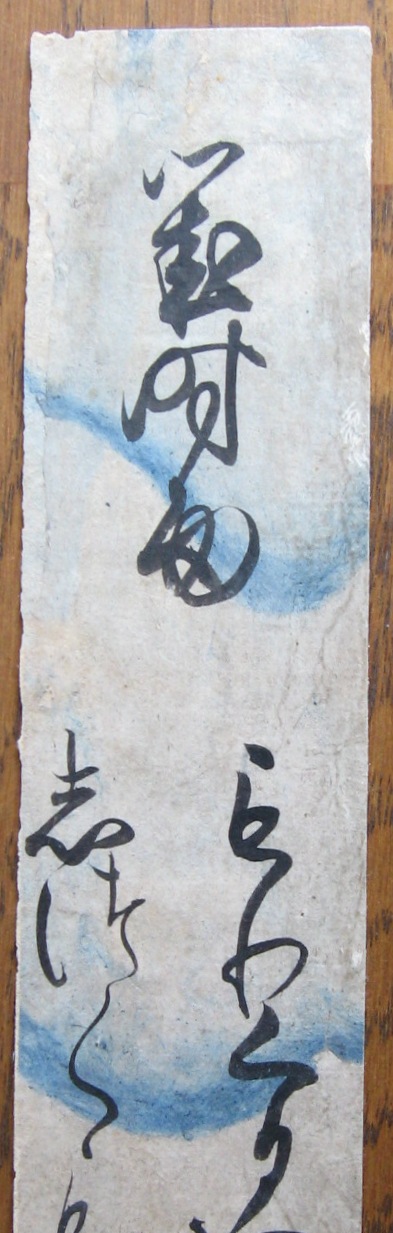
�c���i������j
�ޗNJG�B���A���B�H��t��̊G�Â����ɍڂ�}�Ă����ۍ��ꂽ���̂��ǂ����B
�����i���炤���j
���w����A����ߒ���H�[�̎��ӂ�m�肦��B
���Ԃ̌Ђ��͂���A�\�����������ɂȂ�����ԁB����Ȃ��Ȃ��������g���Ă���̂��킩��B
��h�i����ʂ�j
�����������ォ��ʐF���{�����ƁB���ߒ���m���ŏd�v�Ȃ��́B�Ƃ��ɁA�������Ƃ̂�����肪�m����B
�G���ʖ{�i������@����ق�j
�G�����ʖ{�̑��́B���������ēޗNJG�{�͂��̒���1��Ƒ�������B���������ޗNJG�{�Ƃ����ď̂̔�w�p������A�����ēޗNJG�{�Ȃ��̎g�p�ɑ��Ĕے�I�Ȏ��҂����݂���B�����A���͊G���ʖ{�Ƃ��邾���ł́A������ޗNJG�{�̓��ِ��i�l���E���j�E�ߑ�ł̊��p���̗��j�j��c�����ɂ������Ƃł���B���āA�T�O��̖��ł͂Ȃ��A���j�I���Ƃ��ēޗNJG�{�Ƃ̊֘A������ƁA����������]�˒����̂��̂̑������W���Ă���B�܂�ޗNJG�{�̎���Ɠ������̂̑��������ӂ����̂ł���B�����͕��ꑐ�q�E�@�����E�̎����Ȃǂ���ł���B
�G���Ŗ{�i������@�͂�ۂ�j
�G����������ꂽ�����B�ޗNJG�{�Ƃ̊֘A�������͍̂]�ˑO���̂��̂ł���B�Ê����{�Ɛ��Ŗ{�ƁA�Ƃ��ɓޗNJG�{�Ƃ̊W�͐[���B���Ƃ��ΓޗNJG�{�́w�ɐ�����x�͖{���E�}�G�Ƃ��ɍ���{�̌�����������̂ƌ�����B
�G���i�����Ƃj���撆���i�����イ���j
�G�t�i�����j
�G���t�B���G�t�B������ҁB
�]�ˎ����i���ǁ@�������j
��������ޗNJG�{�̑唼�͍]�ˎ���̐����ł���B
�G�����{�i���ʂ��ڂ�j
�}�G���������́A���邢�͐������ޗNJG�{�������B�����ꂽ�G�͛����Ȃǂɓ\���A�ӏ܂ɋ������B
����Ƃ͕ʂɁA�G����G�{��]�ʂ���ہA�G�̕������ȗ����āA�{�������ʂ����Ƃ��Â�����s��ꂽ�B���������ꍇ�A�e�{�̑}�G�̕������u�G�v�Ƃ��u�G�L�v�Ƃ������Ă������Ƃ�����B
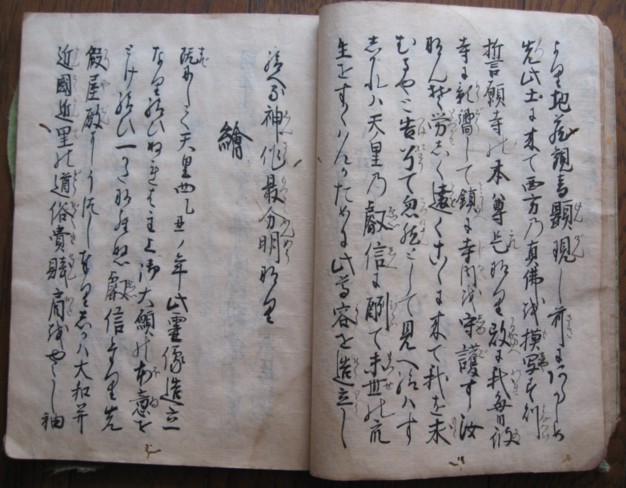
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʓI�ȊG�����{
�G���i���̂��j�@�u�����v�Ƃ��B�D�G��E��G��E�ӕ��E�n����ł���B�痿�̗��q�ɂ͐��e���܂��܂���B�������ӕ��ɍ����ėp������B
�G���i���܂��j
�����ƊG�Ƃ���Ȃ銪�q���̏����B���{�ł͊G�{�����G���̂����������Èȗ��x�z�I�ł������B��������ɂȂ�ƁA�G�{�̑̍ق̂��̂��m�F�����悤�ɂȂ�B�l���w�ɐ�����x�B�ޗNJG�{�Ƃ̊W�͏��G�Ɋւ��ē��ɐ������B���Ȃ킿���G���ْf���č��q�ɉ�������ƁA���^�ޗNJG�{�ɂȂ�Ƃ����̂ł���B�܂�G���̔��W�������������ޗNJG�{�Ƃ������ł���B
�@�G�{���ْf���ĊG�����o���邱�Ƃ́A�܂܍s�Ȃ�ꂽ�B�Â�����Ƃ��Ă͍Y�S�_�Б��w�F��̖{�n�x�Ȃǂ�����B���������ɁA�G�����ْf���ĊG�{�ɉ�����������͂��܂��Ɋm�F����Ă��Ȃ��B�������ꂪ���ۖ��Ƃ��ĉ����̎������Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����̂Ȃ�A�G���i���ɏ��G�j����ޗNJG�{�i���ɉ��^�{�j�֓W�J�����Ƃ����ʐ��́A�����I�ɑ�����ׂ����̂ł͂Ȃ��A�ϔO�I�ȁA�������͒��z�̎����ɂ����Ă̂ݐ��藧���̂Ɨ�������悤�B
�@17���I�̊G���ɂ͓ޗNJG�{�̂����鍋�ؖ{��G���Ŗ{�ƍ�������}�G�̍\�}���U������A�܂��A�{���̕M�v�ɋ߂����̂������邱�Ƃ���A�����Ƃ̊֘A�������ڂ����B
���i�������j
�@�w��̑��q�x�B�H��t��̊G�Â����B��B��a�B
�����i���������j
�{�������ɋL����鏑�ʎ҂Ȃ��������҂ɂ�鎯��B�ޗNJG�{�ɂ͉������Ȃ��̂������ł���B���������ď��ʉ���������ꍇ�͋ɂ߂ē��قȂ��̂ƌ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����͌ʂɍl����ׂ����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����E�i���������j
�{�������ʂ���ۂɁA�{�����ϓ��Ɋ����₩�ɏ����i�߂邽�߂Ɍ����������ł���B�͂𗿎��ɂ��ĂĐ���������B�c���`�m�}���ّ��w�����̑��q�x
�������o�i�����͂������j
�O�\���̏����̕������5�o�̂Ƃ���ɕ͂��������ďo��������̍a�B���������ړI�͖��m�łȂ��B����Ɋ��q�{�̔��o�̖��c�Ƃ����B
�����ڈ��i�����߂₷�j
�{�����ʂɍۂ��A�V�n�ɕ͗l�̂��́i�M�̐K��͂��g�p�������̂Ƃ݂���j���������Ă������E�݁B�j�ڈ��Ɠ����@�\�����B
�������q�i���Ƃ��������j
�������𒆐S���A���̑O��̎���������܂ޒZ�ҕ���B��l������ɂ���ƁA���ƕ��E���ƕ��E�������E�m�����E�ٗޕ��Ȃǂ�����A�܂����{�ȊO��ɂ����ٍ���������B�ޗNJG�{�̑̍ق��Ƃ����`�{�������B
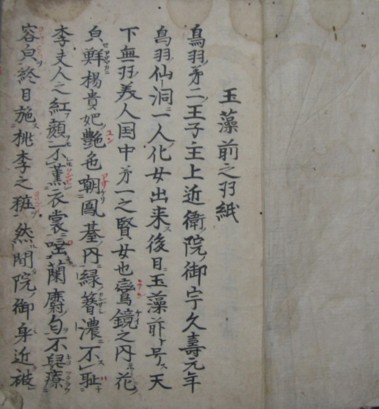
�@�@�@ �@�w�ʑ��̑O�̑o���x�i2�{�̔������d�ς̕���j
�ܖ{���i����ق��j�@�ޗNJG�{�̓����̑���ɐܖ{�͑��݂��Ȃ��B�������ɂ��̂������ɂ���ꍇ������B���w�@��w�}���ّ��w���������Y�x
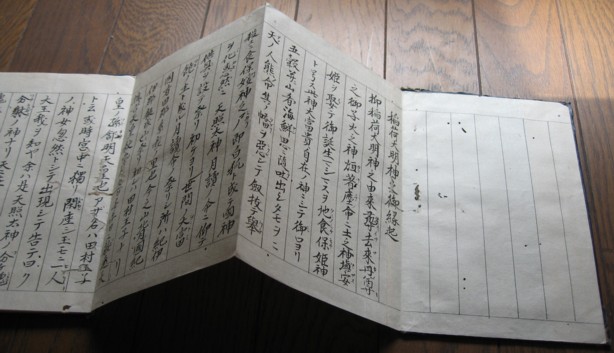
�����i���������j
�\���݂̂ȂǁA�����I�ȏꍇ���������ŁA�Ԃ�����S�����߂�ꍇ������B�Ƃ�킯�ܒԂ���̓ޗNJG�{���G���Ɏd���Ē����P�[�X�͏��Ȃ��Ȃ��B
�L�i�����j
�����i��������j
�ܒԑ��ɂ�����ɂ���A�G�Ȃ����{�������̗��ʂɁA����H����A�K�v�Ȏ������L����Ă���ꍇ������B�����͑}�G�̑}���ӏ���F�ȂǂɊւ��邱�Ƃł���B�Â���ɂ́A�G���ł��邪�A���m��w�}���ّ��w����߂̂܂ցx������B����ɂ́u���ӂ�i�ӕ��j�v��u�Z�i�j�v�Ȃǂ̏���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�z���x������P�}���Ӗ�����}�G������
�̐�G�i�����j
���q�E�ꖇ�G�Ȃǂ̂�����������B�ޗNJG�{�Ɠ������^��ӏ������炵�������̂��̂����邩�璍�Ӑ[������ׂ��ΏہB
�撆���i�����イ���j
�G�̒��ɕ`���ꂽ�G�B�G�̒��Ɏ����Ȃǂ��`����Ă���ƁA���̕����ɛ�����|�����������Ă��邱�Ƃ�����B����ɕ`����Ă���G�������B�ޗNJG�{�̏ꍇ�͛����E�|�����E��ǁE���Ȃǂɂ悭��������B
�@�ŋ߁A�悭�g����悤�ɂȂ����p��ł͂Ȃ����Ǝv�����A�ǂ����낤�B

�撆���i�����イ���j
�G���Ƃ������B�G�̒��ɏ������ꂽ���B�䎌��ȗ��ȏ������Ȃǂ��L�����B�Â��ޗNJG�{�ɑ����B����������ȏ�Ɏ���������]�ˏ����ɂ����Ă̊G���ɒ��ڂ��ׂ����̂������B�����̑����͖{���̈ꕔ�ł͂Ȃ��A�{�����甼�ΓƗ������������Ă���B�Ƃ��Ɍ��ꐫ�ɕx���Ⴊ�����A���ꎑ���Ƃ��Ă����l������B
�@�������q�E�Ï�ڗ��Ȃǂ��܂߂āA�G�����{�ɂ͉撆���̏������ꂽ���̂������B��������͂�䎌�ł��邵�A�������ł���B�ޗNJG�{�S�ʁA�Ƃ��ɍ]�ˎ���O���̓ޗNJG�{�ɂ͉撆�����قƂ�ǔF�߂��Ȃ��B���ĊG���ɂ͂����Ό��o����邱�Ƃ���A�G�����{�̉撆���͊G�����玦���ĕ��y�������̂ł͂Ȃ����낤���B
�撆�����{���i�����イ����ɂイ�ق����j
�}�G�������ɖ{�������荞�ނ������B�撆����1��ł��邪�A������G���Ƃ��Ẳ撆���͖{���Ƃ͓Ɨ������������ł̉�b������������Ԃ���̂ɑ��āA�撆�����{���͂����܂Ŗ{���̈ꕔ�ł���B
�������q�i���Ȃ������j
�]�ˑO���̒Z�ҕ���B���w�j�I�ɂ͂������q�ƕ������q�Ƃ̊ԂɈʒu�Â����Ă���B�A�����̕����͒P���ł͂Ȃ��B�ޗNJG�{���U�������(���Ώۍ�i)�B�����������ς�Ŗ{�����z�����B�G���{�������B���e�I�ɂ͒����̓T�Ђɂ���Ă�����̂������A�}�G�����敗�̂��̂��ڗ��B�ޗNJG�{��E���H���q��w�}���ّ��w���P���x
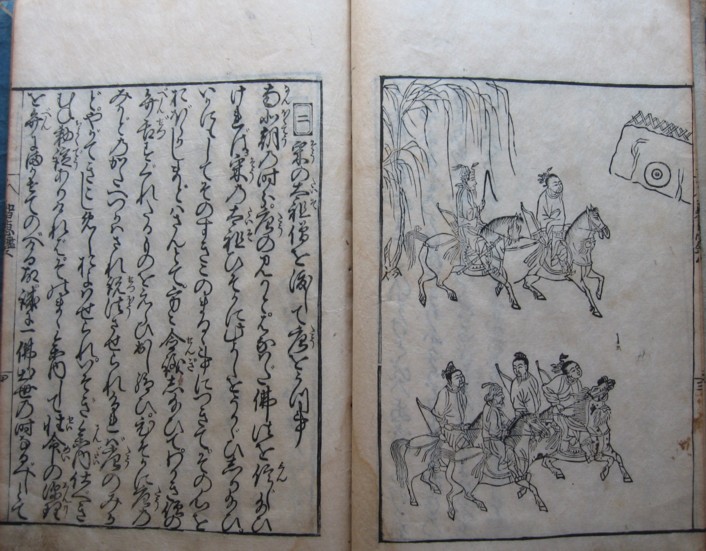
�̗����i���邽�j
�w�S�l���x�w�ɐ�����x�B�ꖇ�����ޗNJG���̓��M��������A�ق��͐����ɒO�Ζ{�̂悤�ȒP���ȍʐF���{�����̂�����B
��a�i���ǂ́j
��a�a���B��������̐����h�������ƍl�����Ă���G���q���B�w��P�����x�ɋL�ڂ����B�u��a�v�̈�����G�������݂��邱�Ƃ���A�G���̐���̔��ɏ�a���ւ���Ă������Ƃ��m���Ă���B
�����i���傤����j���\�E�����i�̂��E���傤����j
�����i���傤����j
�ޗNJG�{�͋��炭�I�[�_�[���C�h�̏ꍇ�������ƍl������B�Ƃ��낪�A�ǂ̂悤�ɍ��ꂽ�̂����R�Ƃ��Ȃ��B���Ƃ═�Ƃ̉œ�����̈�A�܂��I���̒��x�Ƃ����ړI�����邱�Ƃ͊m���ł��낤�B�܂��A�㗬���m�̓y�Y�i�Ƃ��Ă������Ă����B
�s���i���傤�����j
�ޗNJG�{�̍s���́A�Â����͈̂�肵�Ă��Ȃ��B�������A�]�ˑO���̂��̂͌��܂��Ă���B�����̕��╶���̑傫���Ȃǂ̗v���ɂ���ĈقȂ邪�A�����t�����ނ�8�s����13�s���炢�ł���B�s������艻�����i�Ƃ��āA�j�ڈ�������B
�_����i����т��j
�{��������G�ɉ_����������ƁB�H�ł͂��邪�A�␣���ɑ��w�����Â��x�ȂǁA����̎��Ⴊ����B
���i����߁j
�]�ˎ��ォ��ߑ�ɂ����Ă̊Ӓ�Ƃɂ��M�ҁi���ʎҁE�G�t�j����̏ؕ��Ȃ����ؕ��̎D�B�����͌���Ă���B�������A����I�ɂ͋߂��l���ł���ꍇ�������A��ʐ^����˂��Ă��邱�Ƃ����邩��A�Q�l���Ƃ��ĂƂǂ߁A��R���Ă��܂�Ȃ��ق����ǂ���������Ȃ��B�ÕM�̉ƁB
���D�i����ł��j
�u����ł��v�Ƃ������B�������p�E�_�[��ɂ��āA�P�������č��B�\���E���ӁE���ԁE�{�������ȂǁA�������ꂽ���ɂ͍L���g�p�����B
�@������ʎY�^�̓ޗNJG�{�̑}�G������ƁA�e�G�̋��D�g�p�ʂɂ͂����悻�̌������������悤�Ɏv����B���O��`�ʂ��Ă����ʂł́A���D���_�`�Ƃ��ėp����B����A������ʂɂ͉_�`��`�����Ƃ͋H�ł���B���������̕��̋��D�͂ǂ����邩�Ƃ����ƁA�����͛������ǂȂǂ̒��x�Ɏg����̂ł���B
��D�i����ł��j
��̍��q���P�����������́B��ɕ\���E���ӁE���ԁE�{�������Ȃǂ̑����ɗp����B�������}�G���ɂ����������ꍇ������B�Ƃ��ɉ_�`�ɂ�����g�p���邱�Ƃ͍]�ˑO�`�����̂�����ʎY�^�ɑ����B�c�O�Ȃ���A�����ł͑����͎_�����č�����ł���B
���E�i������j
�z�\����1��B�������ɂ����p���邱�Ƃ������B
�_�`�i���������j
�Â��G�����ȗ��p������Ă��Ă�����́B���悻���D�ŕ`����邪�A��D�₻�̑��̐F�̂��̂�����B�]�ˎ���̓ޗNJG�{�́A���D����D���ɓ��ꂳ���B

�O���i�������j�����Ӂi��������j
�����G�i�����j
�w��������x�Ɋ�Â��G�A����ɂ͂���炵���G���w���B�������A�w��������x���ނɂ����G�͛����A��ǁA���Ȃǂ���F���A�Z���A��A�L�A�H�q�ɂ�����܂ł��܂��܂ȕ��ɕ`���ꂽ�B�̂��ɂ͕���⒲�x�i�A���������݂̂Ȃ炸�A�`�ɂ��`�����悤�ɂȂ����B���̊g�U���̒��ŁA�w�����x�Ȃ̂��ǂ���������Ȃ��A�w�����x���ۂ��G���������܂ꂽ�B

���������i���傼������j
�����`������ޗNJG�{���A���������ǂ��ɏ�������Ă������̂Ȃ̂��͖��m�łȂ��B�]�ˎ���A���Ƃ̏����̏������Ă����ޗNJG�{����i�Ƃ��đ����ɏ��n���ꂽ�L�^������B
�\�}�i�������j
�ތ^�I�ł���B�������䂪��{�B�Ŗ{�Ƃ̋��ʐ����ʼn߂ł��Ȃ��B�����G�A�ɐ��G����Ƃ������́B
�H�[�i�����ڂ��j
�ޗNJG�{�͋��s�̒��G�t�ɂ���č��ꂽ�Ƃ����̂��ʐ��ł���B�}�G�͊G�t�A�{���͕M���i�M�H�j�A���̏�Ɋē��������炵���B����Ɛ��{���B�������D���j�q�̕\���͎d���ꂽ���̂��B
�K�ᕑ���i�����킩�@�Ԃ��傭�j
���ƕ��Ƃ���Ȃ钆���|�\��1��B���̐��{�͓ǂݕ��Ƃ��čL���ǂ܂ꂽ�B���̍ہA�ߕt�͏Ȃ���A�P�ɖ{���݂̂����ʂ��ꂽ�B����ɊG�������ƊG���{�ƂȂ�B�ʖ{�E���{�Ƃ��ɍ��ꂽ�B�ޗNJG�{�͂��̂����̊G���ʖ{�̑唼�ɓ�����B
���G�i�����j
��������ɍ��ꂽ�����ȊG���������B�V�n13�`17cm���炢�̂��̂ł���B�]�ˎ���ɂȂ��Ă������ł��邪����Ă���B���m��w�}���ّ��w�������x�A�c���`�m�}���ّ��w���ق났����x
����i������j
�{���〈�Ԃ̗��ʂɊm�F�������́A��M�Œ�������Ă�����́A���C���̂��̂ɐ��������B����ɂ���āA�\�L�̑�����̖{���ٓ��͏��ʎ҂ɂ���ĕK�������d�v�Ȗ��ł͂Ȃ��������Ƃ��@������B�������e�{�Ƃ̋ߎ����̓x���ɂ͌l�������������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���w�@��w�}���ّ��w���킩��b�x�B
�Ï�ڗ��i�����傤���j
�]�ˑO���̑�\�I�Ȍ�蕨��1��B���w�j�I�ɂ͋ߏ��卶�q��̏o���ȑO�̏�ڗ����w���B���Ƒ������E���Љ��N���Ȃǂ̓��e�����B���{�̓ǂݕ����ɍۂ��Ă͐ߕt�Ȃǂ��ȗ������B���̓_�A���̖{�̓ǂݕ����Ƌ��ʂ���B
�ÓT��i�i���Ă��Ђ�j
�w�|�敨��x�w�ɐ�����x�w�Z�g����x�w��������x�w���E����x�ȂǁA���Â̕��ꂩ��ޗNJG�{�͑��݂���B�����R�L����Ƃ��Ắw�ی�����x�w��������x�w���ƕ���x�w�����L�x�w�`�o�L�x�w�]�䕨��x�ȂǑ�\�I�Ȃ��̂͂�������G�{�����ꂽ�B���b�W�ɂ��w��W���x������B���̂قƂ�ǂ͍]�ˎ���ɂȂ��Ă�����ꂽ���̂ŁA��������܂ők�y�ł�����̂͌l���w�ɐ�����x���炢�ł���B�w�ɐ�����x�̑����͍]�ˎ���O�`�����̍�ł���B
�ӕ��i���ӂ�j
�L�k�Ȃǂ��ɂ������́B������P�������Ĕ��F�̓h���ɗp����B�܂����̊痿�ɍ����ėp����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̔����������ӕ��B�������͖n�B200�{
�R���N�V�����i���ꂭ�����j
�]�ˎ���̓ޗNJG�{�R���N�^�[�ɒN������������Ȃ��B���g�̖I�{��Ƃ��l�����邩�B�ߑ�ɂȂ�ƁA����^���╽�o�����Y�Ȃǂ̌ÓT�����҂��A���̌`�Ԃ̓T�ЂƂ��킹�Ď��W�����B���a����ɂ͂������q�������{�i�����钆�ŁA���R�d�����͓I�ɏN�W���A���̑����͍����c���`�m�}���قɎ��߂��Ă���B���A�ޗNJG�{�̒l�i�̏オ��A�l�R���N�^�[�͏��Ȃ��Ȃ��Ă��邪�A�����҂̒��ɂ͏N�W�𑱂���l������B�����������͑�w�}���ق���p�قȂǁA���������˂��@�ւɎ��܂�ꍇ�������Ƃ����̂�����ł���B
�������D�i������ł��j
���D�́u����ł��v�Ƃ��B�ނ���u������ł��v�̂ق����蒅���Ă���悤���B���̎���n�Ƃ��āA����ɋ��D�Ȃǂő������{�����\���̒ʏ́B�����Ȍď̂ł͂Ȃ��B���D�ƂƂ��ɋ�D�����̔��⍻�q�Ȃǂ�p���邱�Ƃ����ʂł���B������ɂ��Ă��������D�͓ޗNJG�{�̍ł���\�I�ȕ\���ł���B
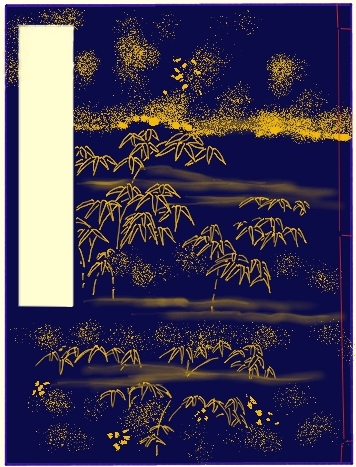
���D�i����ł��j�����D�i����ł��j
�ʐF�i���������j
�ޗNJG�{�̍ʐF�ɂ͐��e�̗��[������B���k�͊G���̂��͔̂Z�W������B�܂��A��̐F�����┧�F��n�ɂ��Ėj�ɍg�������A�\��̒��J�ɕ`���B����A�e�G�ȊG���̂ق��́A�����Ƃ��ĒP�F�Ŏ�����`���ĔZ�W�����Ȃ��B���`�ɒ����ȓh��������Ă��Ȃ��ꍇ�������B�܂��A�n�̐F�ł����Ă������z��p����ꍇ�ƌӕ��ɗ��F�̐����������ėp����ꍇ�Ƃ�����A�����͂����Γ����ʏ�ɂ����ĕ��p�����B
�ْf�i��������j
���{��������ŁA�V�n��萮���邱�ƁB����ɂ���Ė{���Ɏx�Ⴊ�o�邱�Ƃ͂Ȃ��B�}�G�Ɋւ��ẮA�V�n�͑�T�������Ő�߂Ă��邩��A���Ɏ�����Ȃ��Ȃ邾���ŁA�G�̕`�ʂɍ�����肪�o�邱�Ƃ͋H�ł���B�{����}�G�̗��ʂ̏�����}�G�ԍ�����Ă��邱�Ƃ����邪�A��������ŏI�i�K�ōْf���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���̂ł���B
�}�G�ԍ��i�������@���j
�}�G�����̗��ʂȂǂɏ������ꂽ�ԍ��̂��ƁB���Ƃ��Α}�G��1����10���p����ꍇ�A�e�}�G�ɂ��ꂼ��1����10�̊�������n�������B�㉺2���{�̏ꍇ�́u���v��u����v�ȂǂƋL�����B���̂悤�ȕ\�L�́A���Ƃ��Γy���h�̊G�����{�Ȃǂɂ������A��ʓI�ɗp�����Ă������Ƃ����������B�������w�Y�����Y�x����{�̏ꍇ�́u���炵�܈�v�ȂǂƂ�����邪�A���̂悤�ȁA�q�������{�ԍ��r�ɂ��\�L�@�́A�ޗNJG�{�Ǝ��̂��̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B�܂�A�����ė����������邱�Ƃɂ��A���̑}�G�Ƃ܂���ʂ悤�ɍH�v���Ă���Ɛ������邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��A���̔ԍ��́A�����͗����̗��ʂɏ������̂ł��邪�A�\�A�܂�G�̕`����Ă��鑤�̉E��Ȃ�������̋��ɋL����邱�Ƃ�����B
�_���i���j
��D�E�┓�E�⍻�q���_�f�Ɖ��w���������č����Ȃ邱�ƁB��D�̉_�`��G�̒��̌��Ȃǂɂ����Ό�����Ƃ���ł���B
���G�i�������j
�{�������ɋ��D���D�Ȃǂŕ`�����G�╶�l�B���G���͕̂������ォ�瑶�݂���B�ޗNJG�{�ɗp��������̂́A��������Ԓ���P�F�ŕ`�����ȑf�Ȃ��̂ł���B���ؖ{�̒��ɂ�30��ȏ�̊G�����g�����̂�����B�قƂ�Ǔ��M�����A�����܂�ɐ���������B���V���}���ّ��w�J��ǂ�x
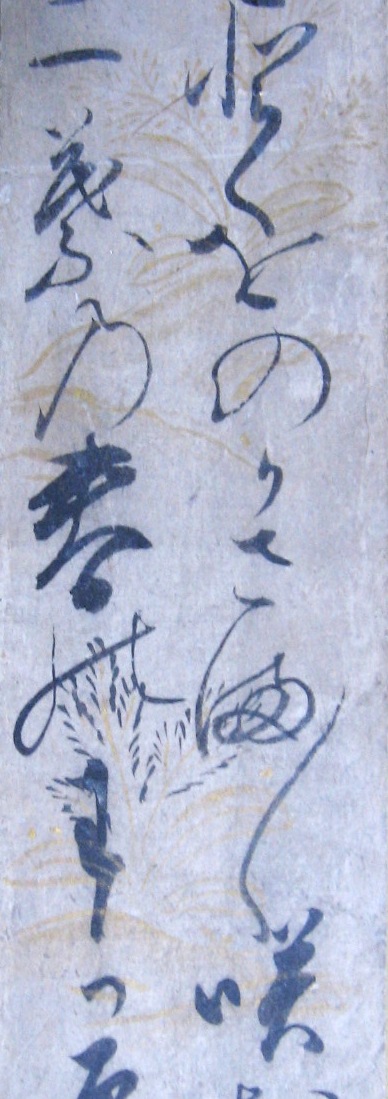
�����i���������j
�����ȕ`�ʂ̏ꍇ�Ƒe�G�ȕ`�ʂ̏ꍇ�Ƃ͈Ⴂ��������B��҂̏ꍇ�͂����Ζڈ����x�̂��̂Ƃ��Ĉ����A�G�Ƃ��č̗p����Ȃ����Ƃ������B
���~�i���������j
�ޗNJG�{�̗����͒��̎q���Ȃ����Ԏ������Ȃ̂ŁA����ł���B���������Ė{�����ϓ��ɏ��ʂ���⏕�ƂȂ鉺�~��p�������ǂ������R�Ƃ��Ȃ��B�������A�{�����ʂɏc����n�������`�{���m�F����Ă���B���̂��Ƃ���A�g�p�����\���͔ے�ł��Ȃ��B�����A�����͐j�ڈ������邱�Ƃʼn��~�̑�ւɂȂ��Ă����̂�����A�d�v�Ȃ��̂ł͂Ȃ������ƍl������B
�����i���債�j
�ޗNJG�{���ǂ̂悤�ɔ̔�����Ă����̂��͖��炩�łȂ��B�����{���ƌĂ��Ƃ�����d�_�I�ɒ��ׂ�Ƃ�����������Ȃ��B
���n���i�����ڂ����j
�ޗNJG�{�̒��ł́A��q��|����Ȃǂ̉撆��Ƃ��Č�����B���̏ꍇ���n�ɂ���ĕ`����Ă���B

�Z�g�h�i���݂悵�@�́j
�]�ˎ�����\�����a�G��1�h�B
�������i����肪���݁j
�G�̓V�n�ɕ`�������̈��B��ɐn�̍ʐF���{����邪�A�Â��ޗNJG�{�ɂ͓��F�����p�����B���̓_�A�œܕ\���ƒʂ�����̂�����A���ӂ����B�܂����ؖ{�͖��n�ɋ������U�炷�̂��T�^�ł���B�]�ˑO�E�����̂��̂ɂ͗]���Ȃ������Ŗ��߂���̂����Ȃ��Ȃ��B�֊s�͍����E�n�̐��E��������B���ؖ{�͍����̏�ɋ������d�˂���̂������B�`�Ԃ͒����̃o�[2�w����3�w���x�ł��邪�A�Â����͔̂g��̃o�[�ɂȂ��Ă�����̂������B���̒n�݂͐��������F���嗬�ł���B����͌ӕ��ƗL�@�n�̐����i���G��j�Ƃɂ����̂ł���B�����i�����݁j
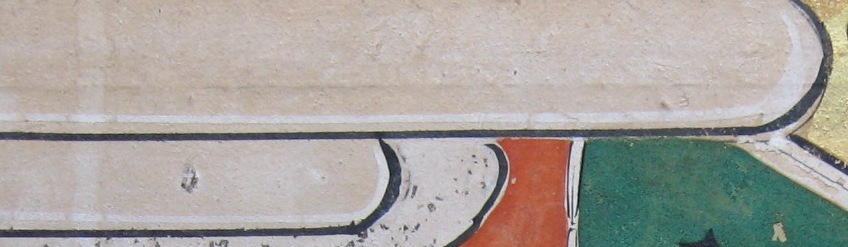
���{�i�����ق�j
�ޗNJG�{���ǂ��ŁA����ɂ���Đ��{���ꂽ�̂��́A���݂̂Ƃ��떾�m�ɂ���Ă��Ȃ��B�{�����ʁE�}�G��恨�{�������Ƒ}�G�����Ƃ̌Еt���V�n�Ȃǂْ̍f���\���̎�t���Ԃ����J�������ʂ��Ƃ����ߒ��܂���̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B
���o���i�������傤�Ԃ��j
��������ߐ��ɂ����ė��s������蕨��1��B�K�ᕑ�Ȃ�Ï�ڗ��Ɠ����悤�ɁA�ǂݕ��Ƃ��Ă�����A�G�{�Ƃ��č��ꂽ�B�ޗNJG�{�����ꂽ�{���ɂ͐ߕt�͏Ȃ���Ă���B���̓_�A�K�ᕑ�Ȃ�Ï�ڗ��̏ꍇ�Ɠ����ł���B�w�����P�x
�������i�������傢��j
�����҂̈�L�B�ޗNJG�{�̃R���N�^�[�̑�����Ƃ��đ�\�I�Ȃ��̂ɉ��R�d�̐Ԗؕ��ɂ⍕��^���̍��앶�ɂ̂��̂�����B
�����t�i�������傭���j�@
�}�G�̑���������S������G�t�B���m�̑����ʖ{�Â���ɂ͂��������l�������悤������A�ޗNJG�{���������Ǝv���A�Ƃ肠���������Ă����B����_�`�S���̐l�B����A�����܂ŕ��Ƃ���K�v���Ȃ��������B�ǂ��Ȃ낤(?_?)?
�����i���傤�j
�ޗNJG�{�̑����ɂ͒����E�l���E�j��E���݁E����E�Д����E�痿�����Ȃǂ���������B��ʂɒ��̎q����Ԏ������͒������Ȃ��Ƃ����邪�A���ۂ͞����قǂłȂ��ɂ���A���ɂ�鑹���͑����B�������S�ʂɖ{���Ɏx�Ⴊ�ł�قǂ̒����͊m�F����Ȃ��_�͓ޗNJG�{�̓����Ƃ�����B�l���͑l�ɂ�銚�ݏ��B�Ђ̔����͕\���ƌ��ԂƂ�������邱�ƁA�܂����ӂ�������邱�ƁB�Ƃ��Ɍ�҂́A����ɂ���ĊY�{�̏������킹���邽�ߐ[���ł���B�痿�̔����́A���̐�����A�d���Ȃ����A�悭������Ƃ���ł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�痿�̔���
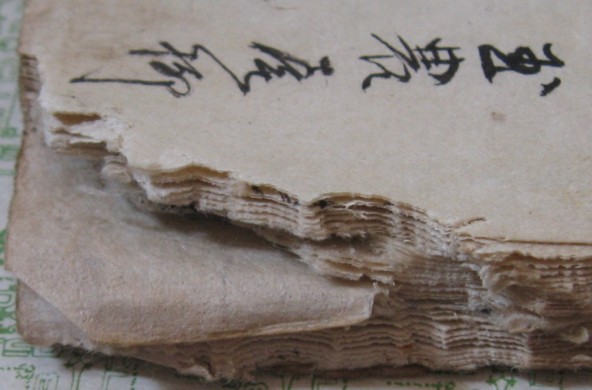
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�ɂ�����ꂽ��
�����i��������j
�\���̒����Ȃ��������ɓ\���鏑�����L���������ŁA��ɒ��̎q�����p������B�O���1��B�ޗNJG�{�ł́A�قڑS�Ăɂ����ĒZ���l�̑����������g�p�����B�ޗNJG�{�͓�������Ȃ����̂��قƂ�ǂȂ̂ŁA���ӂ�������ƈ햼����Ƃ��Ĉ�����ꍇ�������B
�I���{�i���Ȃ�����ڂ�j
���x�i�Ƃ��Ă̏��ЁB�̂╨��̑��q�Ⓜ�{���D�܂ꂽ�B�ޗNJG�{�͂��̈��Ƃ��Ď��v����邱�Ƃ��������Ǝv����B
�O�Ζ{�i����낭�ڂ�j
���{�̑}�G�ɒO�E�E����Ȃǂ̐F��2�`3�F�p���đ�܂��ɍʐF���{�������́B���a���犰���E����ɂ����邨�悻50�N�Ԃɍ��ꂽ�B���i���ɐ���ɍ��ꂽ�Ƃ�����B���������ČÊ����{�Ɛ��Ŗ{�Ƃ̗����{�����݂���B�O�G�Ƃ͒��ڌ��т��Ȃ��Ǝv���B
���i���j
���Ђ�ی�E�ۑ����邽�߂̖ؐ��Ȃ��������̗e��B
�U�����i���炵�����j
�������A�s�̋K���ɂ�����炸�Ɏ��R�Ɏ��ʂ�p���ď����L�����@�B�ʏ�A�a�̂̕\���ɗp������B�������A�ޗNJG�{�ɂ������Ό�����Ƃ���ł���B����́A�����ɑ}�G���z�����ꍇ�ł���B�܂�A���ɑ}�G������}�ނ��Ƃ����炩���ߐݒ肵�Ă��āA���{���������ŏI�s�܂Ŏ��炸�ɗ\��̖{���������I����ƁA���ʂɗ]�����ł���B������L���ɗp���邽�߁A�����܂ł̐��s�������R�ɎU�炵�ċL���̂ł���B���̕\���͑��ʂł���A�a�̂̐F���Ƃ͈Ⴂ�A�M���̗V�ѐS�����������镔��������B
�D�G�i�ł����j
�D�i�ł��j��p�����G�B�D�Ƃ͋����q�E�⍻�q���P�ŗn�������̂ŁA������痿�Ƃ��ĊG��`�����Ƃ͌Â�����s�Ȃ�ꂽ�B���ɐ�̊G�ɂ����Ă͓D�G���嗬�ł������B�D�G�i�ǂ낦�j�Ƃ͕ʎ�B
����{�i�Ƃ������ق�j
�u�Ƃ������ڂ�v�Ƃ������B�ޗNJG�{�̒��ł����Ƃ��傫�Ȑ��@�ɗނ�����́B�c��30cm�E����17cm�̖{�B�H�ɉ��^�̓���{�����݂���B�����鍋�ؖ{�ƌĂ����̂́A��������ɑ�����B��O�͊m�F����Ȃ��B
�y���h�i�Ƃ��@�́j
��a�G�̑�\�I��1�h�B�ޗNJG�{�̍��ؖ{�̊G�́A���ɓy���G�Ƃ��y���G���Ƃ�������B���ۂ̂Ƃ���͕s���ł���B�������y���h�Ɋw��A���邢�͓y���h��͕킵�����G�t�͏��Ȃ��Ȃ��������낤�Ƒz�������B
���̎q���i�Ƃ�̂����݁j
�㎆�̂P��B����̂��̂��甖��̂��̂܂ł���B�ޗNJG�{�ɗp��������̂͌��肪��ł���B�Ƃ��ɗ��̂��́B�ܒԑ��̂��̂́A�Жʏ��ł�������A�K����������ł���K�v���Ȃ��B������A��┖��̂��̂�������B
�D�G�i�ǂ낦�j
�D�G���p�����G���1��B�]�ˌ���ɗ��s���A�����Ɏ����Ă����ꂽ�B�ޗNJG�{���D�G���p���č������̂����A�D�G�Ƃ͌ĂȂ��B�܂��A������D�G�Ƃ̒��ړI�ȊW���Ȃ��B�D�G�i�ł����j�Ƃ͕ʎ�B
�D�G���i�ǂ낦�̂��j
�ӕ����������p�E�_�[��̊G��B�ޗNJG�{�̎�v�痿�B�w�l�όP�}�b�x�u�o�t�v
�����i�Ȃ������j
�{���̖`���ɋL�����^�C�g���B�ޗNJG�{�̏ꍇ�A����͌����Ƃ��đ��݂��Ȃ��B���������āA����̂�����͓̂���Ƃ��āA���̓���v���𖾂炩�ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���H�w�G�X�q�܁x
�ޗNJG�i�Ȃ炦�j
�D�G���p���ĕ`���ꂽ�G���1��B�t�ق̊ς̂�����̂ŁA�����������]�˒����ɂ����č��ꂽ�B��E�c��ȂǁB
�ޗǐ��i�Ȃ炨�����j
���ƁA�ޗǂō��ꂽ��B�ޗNJG���̊G�������B�ޗǐ�͍����ɂ�����܂ō���Ă���B���ɂ͖����܂œޗlj��Ƃ������Ƃ�����A�����ł͌i�i�Ƃ��ē��l�̓ޗǐ��z���Ă����i�ΐ쓧�搶�̌�_���݂�j�B����ƓޗNJG�{�Ƃ̂Ȃ���͕s�ځB���̐��ԕ��Ă̊G��ޗNJG�Ə̂��邱�Ƃ���A�������ɗސ��I�ɓޗNJG�{�Ƃ����ď̂����܂ꂽ�Ƃ����̂��ʐ��ł���B
�P�i�ɂ���j
�D�G����G��A�ӕ��Ȃǂ͐��ɗn�������ł͎��ɌŒ肵�Ȃ��B��������Ƃ܂������ɖ߂��Ă��܂��̂ł���B������Œ�܂������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B���̌Œ�̂��߂̐ڒ��܂̖������ʂ������̂��P�̏`�ł���B
�\�E�����i�̂��E���傤����j
�����ɑ听���ꂽ�|�\�B����ŁA�����f�ނƂ��ĕ��ꂪ����邱�Ƃ������������B���̕��ꂪ�ޗNJG�{�����Ă���P�[�X���U�������B�\�u�E���v�Ɓw�ʑ��̑O�x�Ƃ̊W�ɂ݂���悤�ɁA�\����̉��o���G�ɔ��f����Ă�����̂�����B
�Еt�i�̂�Â��j
���ӂ�\�邱�ƁE�\���ƌ��ԂƂ�\�肠�킹�邱�ƁE�{�������Ƒ}�G�����Ƃ�\�肠�킹�邱�ƁB����3�_���ޗNJG�{�ɂ�����Еt�ł���B��3�̃P�[�X�ɂ�2�`3�̕��@������B�ܒԑ��̏ꍇ�͖{�������̏����̕������Б�ɂ��āA3�`5cm�قǐ܂�Ȃ��ē\�荇����B�}�G�����̂ق���܂��ČБ�Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ł���B���̏ꍇ�͗����̗��ʑS�̂��Б�Ƃ���B
���i�͂��j
�������ɂ߂Ĕ������ׂāA������ׂ��ɐ��č�������́B����̎�ނ�����B��3�`5cm�̐����`�Ⓑ���`�ɂ���̂���ʓI�B�ق��ɁA�ג���������є����Ő���ĕs��`�̂��̂ɂ������Ȃǂ�����B�\������ӁA���ԂȂǂ̑����ɂ͌������Ȃ����́B���ؖ{����̓ޗNJG�{�̂������ɂ͂���𑽗l������̂������B�܂��A�}�G���̉_�`�⒲�x�i�E��ǂ̊G�̒n�Ȃǂɂ��p������B
���i�͂��j
���Ђ������ؐ��̗e��B�������h�������ł���B�ޗNJG�{�ɓ������畍���Ă��锠�ɂ͊O��Ɠ��M�ŊW�ɋ�����������Ă�����̂������B
�j�����i�͂肯��Ƃ��j���j�ڈ��i�͂�߂₷�j
�j�ڈ��i�͂�߂₷�j
�{�������̊Ԋu�Ɉ��̍s���ŏ����Ȃǂ̖ړI�ŁA�����̓V�n�ɊJ����ꂽ�����Ȍ��B���̊J���悤�ɂ́A10���p�^�[���m�F�����B���ɂ͉����E�ƕ��p������̂�����B���̏ꍇ�͂ނ���E��������ړI�Ō����J�����̂��낤�B
�@���̗��j�́A�nj��ł͎�������̎��Ⴊ�����ł���B���̑��ɂ��A�ޗNJG�{�ȊO�̎ʖ{�ɂ����Ă��������Ɏ���܂Őj�ڈ����p����ꂽ�B���������ӂ��ׂ��͓ޗNJG�{�ɂ����Ă͐j�ڈ��̎�ނ����l�ł��邱�Ƃł���B�����炭�ޗNJG�{�̏��ʂ���Ƃ���E�l�ԂœƎ��ɔ��W�������̂Ǝv����B
�@���āA�j�ڈ��͖{���}�G�Ɍ����Ă݂�����̂ł͂Ȃ��B�撆�����{���ɂ��g��ꂽ�B������G���ɂ͌��o����Ȃ��B���w�@��w�}���ّ��w���������Y�x�ȂǁB�G�̗]���ɖ{�����������ނ��̂̒��ɁA�j�ڈ���������̂�����B�G���̉撆�����{���ɂ�����g�������̂͂Ȃ�����A��͂�A�ޗNJG�{�Ǝ��̂��̂ƌ���ׂ����낤�B

�����{�i�͂ڂ�j
�������B�������܂�ɂ����T�C�Y�ŁA���Z������⏬���߁B
�H��t���i�Ђ�����@����̂ԁj
�]�ˎ���O���̑�\�I�ȑ�a�G�t�B�헤���o�g�B���M��݂̂Ȃ炸�A�Ŗ{�}�G�������肪�����B�G�����͓`�����邪�A�ޗNJG�{�Ɏt���Ƃ�������̂͊m�F����Ȃ��B�������A����ɑ��Ċ��{�̑}�G�𑽂��肪���Ă��邱�Ƃ��ǂ���������悢���B�ʖ{�̍��q�{�̑}�G���Ȃ��āA�G���ɂ͂���̂ł���B
�M���i�Ђ������j
���L���ł��邽�߁A���ʎ҂̎��̂͏ڂ炩�łȂ��B���q�d���B���ؖ{�̏��ʎ҂͊G���̏��ʂ����˂Ă����B�����鍋�ؖ{�͗�O�Ȃ��\���̎�ɂȂ�B
�S�l����i�ЂႭ�ɂ�����j
�u�ЂႭ�ɂ�v�Ƃ����̂����p�I�ɂ͓K���B�w�S�l���x�̊G���ʖ{�ɂ́A������ʎY�^�ƌĂ��e�G�Ȃ��̂͂Ȃ��悤�ł���B
�\���i�Ђ傤���j
�ޗNJG�{�̕\���́A�ʏ�A�������D��œ܂Ƃ���������������ł���B�j�q���̂��̂����Ȃ��Ȃ��B
�����i�т傤�ԁj
�ޗNJG�{�͗������ْf���A�����\��t���������͍�������`����Ă���B�G�݂̂̂��̂�����B�܂��������甍��������t�͐���������B�܂��A�]�ˑO���̛����A���Ƃ��s�K�}�◌�����O�}�̒��ɂ́A�ޗNJG�{�̊G�Ƌߎ�������̂�������B�Ȃ��A�ޗNJG�{�̉撆��A���Ȃ킿�}�G���ɕ`����雠���́A�ʏ�A���i��ł���B
�ܒԑ��i�ӂ���Ƃ��j
�������O���ɐ܂��đ��ˁA�̂ǂ̕��Ɍ����J���A���ŒԂ��鑕��̕��@�B�ʏ�4�c�ڂƂ���4�����Ɍ����J���Ď���ʂ����̂����A����{�̏ꍇ��5�c�ڂƂȂ�B
�M�i�ӂŁj
���̂Ƃ��돑�����ƂȂ�orz
�G��`���̂ɉ��{���炢�g�����̂��낤�B
�U�艼���i�ӂ肪�ȁj
�U�艼����1���������͑S���̖{���������I���Ă���A�����l���ɂ���Ă�����B���w�@��w�}���ّ��w���킩�x���w�Ƃ̔�r
���{�i�ӂ�ۂ�j
��{�ƂȂ�T�̎ʖ{�B�ޗNJG�{�̍\�}�⎖���̌^�͗ތ^�I�ł��邩��A��̉\���Ƃ��ĕ��{�����݂��Ă������Ƃ��l������B�������A���܂��ɂ��̎�̎����͔�������Ă��Ȃ��B������̉\���Ƃ��ẮA���X���{�͑��݂��Ȃ������Ƃ��l������B�G�t�̌o���Ɉˑ����邩�A�ʂ̓ޗNJG�{���苖�ɂ����ĎQ�l�ɂ������Ƃ��z�������̂ł���B
�ڂ���
���G���n�i���E��j�̔Z�W�ɂ���ė֊s�����܂���Z�@�B���̊O���i�֊s���̑��j��������ɂ����đ����p������B
���̖{�i�܂��̂ق�j���K�ᕑ�ȁi�����킩�Ԃ��傭�j
�Ԏ������i�܂ɂ������݁j
��ʓI�ɂ͒��̎q���ɊD�Ȃǂ��������A���炩���D�F�������������B���ʏ��ɂ͓K���Ȃ��B�ޗNJG�{�ł͒ʏ�ܒԑ��ɗp������B���̎q���������������邱�Ƃ���A�e�G�ȗʎY�^�̉��^�{�ɕp�p�����B���������ȓ���{�ɂ��A���̎q���ƌ��ʓI�ɕ��p����Ă���Ⴊ����i���V���}���ّ��w���[�x�j�A�g�p���@�ɂ͗�O�����݂���B�����i�����{�s���j�����Y�n�Ƃ��ČÂ����璘���B
�����i�݂������j
�\���̗����B�ʏ�A����������Ă��Ȃ��B�ޗNJG�{�̏ꍇ�͖{���������A�������͑����������g����B
���ԊG���i�݂����j
�Ìy�́w�F��̖{�n�x�A���Â̓����A�����̃I�r�V���A���여�̊G���A�w���������V�b�x
���������i�ނ�܂��@�������j
1392�N�A��k�������ꂵ�A�ȗ��A1573�N�A���R�����`�����Ǖ������܂ł��ꉞ�������������B�ޗNJG�{�����܂ꂽ����ł��邪�A����������̂͋ɏ����ł���B���������������s�ڂ̓`�{�������A���̒��̂ǂꂪ��������̍�ł��邩�́A�����̏ꍇ�A�l�I���f�Ɉς˂��Ă���̂�����ł���B����͉Ȋw�I�ȑ���@������K�v���傫���ł��낤�B
���f��
�ޗNJG�{�̊G�̐���ɂ�����A���f���ƂȂ����Ǝv�����i�ɂ́A�܂��w��������x�w�ɐ�����x�ȂnjÓT�I�ȊG���Ƃ���Ɋ�Â��G�����{�Ƃ��l�����邪�A������ꂾ���ł͂Ȃ��B�]�ˑO���̊G���Ŗ{�Ƃ̊W���������Ȃ��B�w�U�����x���w�c���̑��q�x
���^�{�i�悱�����ڂ�j
���{�Ƃ��B�^�e�������R�̂ق������@�̂��鏑�^�̖{�����^�{�ƌĂԁB��ʓI�ɖ{�̂������Ƃ��āA����͓���Ȃ������ł��邪�A�������ޗNJG�{�̑����͂��̑̍ق��Ƃ��Ă���B�����Œʏ�̏��^�ł���c�^�̖{�������đ��ΓI�ɏc�^�{�ƌĂԏꍇ�������B���Â����̂̓^�e17cm�~���R23cm���x�̂��̂���ʓI�ł��邪�A��������O��̗ʎY�^�Ƃ��ڂ�����i�Q�ł�15cm�~20�`22cm���x�̂��̂��قƂ�ǂł���B
�œ��{�i��߂���ڂ�j
�œ��蓹��̈�Ƃ��Ď��Q�����{�B�����������̉̂╨��̑��q�⊪������B���̒��ɂ͓ޗNJG�{���܂܂�Ă���B�ŋ߁A����Ɠ`���̖{�ŏڂ������ׂĂ���l������B�܂��w����x�i������p�فj�Ƃ����}�^�͎����ɕx�ށB
�����i��傤���j
�{���������͑}�G�Ɏg�p����鎆�B�ޗNJG�{�̏ꍇ�͒ʏ풹�̎q���������͊Ԏ������ł���B�]�ˏ����ȑO�̍�i���ɂ͔㞸������������悤�����A���ʍ���B
�֊s�i����j
�}�G���̎����₷�����E�_�`�Ȃǂ̊O���̂��ƁB��⑾�߂̖n�����������A����͉��`�̃��C���ł���B���ؖ{�̊G�̗֊s�͋ɍׂ����C���ŕ`�����B�������̗֊s�͍����Ɍ���Ȃ��B�����������͒n�̐F�ɗނ���G�̋�p������B

��t�i�ꂢ�悤�j
���q�̒f�ȁB�ޗNJG�{�ْ͍f����Ď����ɂ��ꂽ�蛠���ɓ\��ꂽ�肷�邱�Ƃ����������B���̂��߁A�f�Ȃ̂������œ`��������̂������B
���i����傤�����j
������5�`10�����x���ˁA�����ɐ܂�Ȃ��Ď��Ŋ���A������P�`5���荇���ĕ\�������Đ��{�������́B��a�ԂƂ������B�{���͗��ʏ��ƂȂ�B�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�����ɂ͌���̒��̎q�����g����B�]�ˊ��̂�����c�^�{�ɑ���������B�]�ˏ����ȑO�̓`�{�͊m�F����Ȃ��B���̏��^�͏��i�Ƃ��Ă̎ʖ{�i��������ʖ{�j�ɂ����݂��A���\���Ƃ̎�ɂȂ���̂ł��邱�Ƃ��l�����킹��ƁA���̓ޗNJG�{�́A���̍������悤�ɂȂ������̂ł͂Ȃ����Ɛ��������B